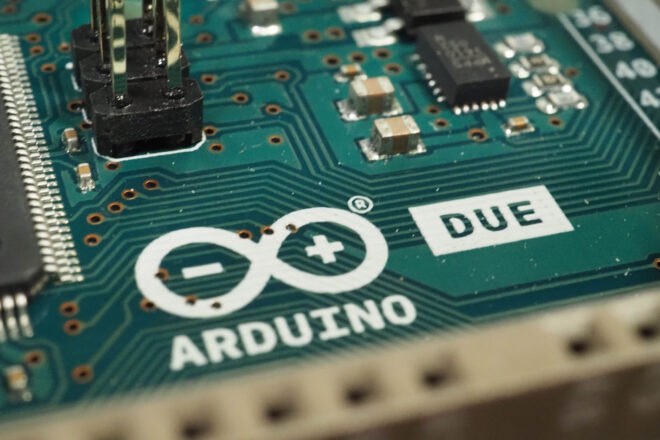こんにちは。Matsuです。
社内備品管理システムを作るお話の続きです。前回は概要しかお話できていませんでしたが、今回から設計の準備段階に入ります。
対象備品の決定
まずはどうやって備品の数量を計測するかを決めて、対象とする備品を決定します。
第1回では、ICタグ等の案も書きましたが、結局のところ重量を測定して数量を計測しようとなりました。(ICタグの購入、管理などはちょっとハードルが高いため)
重量の計測は、市販のロードセルモジュールをマイコンに接続して行います。こちらで紹介されているような感じです。
次は、この計測方法に合った対象備品を選定します。
条件は上記のとおり「重量により数量の計測が容易なもの」と「社内である程度コンスタントに消費されているもの」としました。あまりに重量が軽いクリップや使い切ってもほぼ重量が変わらないテプラのテープカートリッジ、あまりに大きくて重量計の作成が困難なものは除外します。また、あまりに使用頻度が少なかったりする備品も除外しました。
最初は欲張らず、少数からスタートということで 結果、「乾電池」と「ペーパータオル」の2種類に決定しました。どちらもそれなりにコンスタントに使われている、かつ重量により数量の計測が簡単そうなものです。
このシステムがうまくいって、社内に需要があれば、対象を増やしていこうと思います!
ユースケースの整理
ここまでは「備品管理システム」の実際の運用はめちゃくちゃふんわりとしていました。ここでシステムの作成に先立ってユースケースの整理をしておきます。

ユースケース図を作成して、メンバー間で認識の統一を図りました。今後作成していく上でこのユースケースもブラッシュアップされていくと思います。
ここで「API」としているのはバックエンド(クラウドや自社サーバ等…)を示しています。
左端は利用者で、右端は管理者になります。利用者は備品の取り出しや補充をするだけです。それにより組み込み機器が重量の変化をAPI(バックエンド)に通知します。API(バックエンド)では在庫の数量を管理しています。組み込み機器から重量が送られると、それにより在庫の数を再計算します。あらかじめ指定した下限値を下回ると警報として管理者にメール通知、webアプリにも同様の警告表示をします。
管理者は、webアプリを通じて備品の種類の登録、変更、削除、また現在の在庫の数量の確認や、消費傾向の確認ができるようにします。
現状の課題としては
- 組み込み側に、備品情報をどこまで、どのように持たせるか。
- 組み込み側と、API(バックエンド)の連携をどのようにするか
- 管理者から組込側への備品情報の書き込みをどのようにするか
といったものがあります。このあたりは今後詳細を詰めていくときには潰していきましょう。
次回はもう少し具体的な機材、技術要素の選定などまで進めたいと思います。
関連記事
-
こんにちは、アバンセシステムのTIGERです。今回は、3Dスキャン技術を使って3Dオブジェク...
公開日:2023.04.14 更新日:2023.04.14
-
はじめまして、アバンセシステムのTIGERです。よろしくお願いします。 今回はRaspber...
公開日:2022.09.09 更新日:2022.09.09
tag : IoT Raspberry Pi
-
ラズパイ実験室 〜いろんなmicroSDで性能を測ってみた〜
こんにちは! IoT時代到来の真っ只中ということで、弊社でも数多くのセンシングデバイスを取り...
公開日:2021.04.30 更新日:2021.06.29
tag : Raspberry Pi
-
こんにちは!Matsuです。 Arduino、便利ですね。今年は久々に新機種も発売されてます...
公開日:2023.10.06 更新日:2023.10.06
-
WSL2でLocalStackを使ってLambda を実行してみる~実行編~
こんにちは、motoKNです。前回 の続きとなります。 それではローカル環境にLocalSt...
公開日:2023.01.13 更新日:2023.01.13
tag : クラウド
-
WSL2でLocalStackを使ってLambda を実行してみる~構築編~
こんにちは。ラボ記事投稿2回目のmotoKNです。 私自身、今のところ業務でクラウド環境を使...
公開日:2022.09.23 更新日:2022.12.08
tag : クラウド